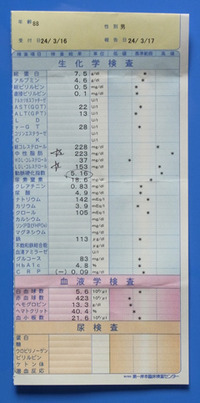2009年01月30日
散歩道で
 昨日の散歩道で 新しいアパートが建てられていた。 札幌市の前年10月の統計数字を見ると 人口は 1,898,473人で 対前年同月比は 0.2%増 世帯数は 878,345世帯で 対前年同月比は 1.4%増となり 世帯数の伸びが 人口の伸びの 7倍になっていた。 世帯分離の増加で 小面積のアパートの 需要が 札幌市に増えるのは 社会的に当リ前のようだと 納得した。
昨日の散歩道で 新しいアパートが建てられていた。 札幌市の前年10月の統計数字を見ると 人口は 1,898,473人で 対前年同月比は 0.2%増 世帯数は 878,345世帯で 対前年同月比は 1.4%増となり 世帯数の伸びが 人口の伸びの 7倍になっていた。 世帯分離の増加で 小面積のアパートの 需要が 札幌市に増えるのは 社会的に当リ前のようだと 納得した。世帯が多くなると 当然に 電気の使用量が増える。 このアパートに電気を引くために 通路を遮断して 電気工事をしていた。 暫く 足止めをされた間に 電気と環境についての 関連が 電気のように 頭を駆け回った。
電気のエネルギー(「 E 」以下同じ)は 石油等の化石燃料のEと異なり 殆ど 備蓄できないので 常時生産し続けなければならず CO2が増え続ける。 そうだとすれば 電気の使用を節約するより CO2を排出しづらい 発電方法を 考えることの方が より現実的だ。
乾電池・蓄電池・燃料電池等の 電気化学反応を利用する 科学電池は 備蓄能力はあるが 発電量も備蓄量も小さい。 新しい発電装置としては 光電効果や熱電効果を利用する 物理電池がある。 光電効果を利用するものには 太陽電池 熱電現象を利用するもののは 熱電池がある。 この二つは 光Eや熱Eを 直接 電気Eに変換できるので 効率は良いが 実際には 発電量も備蓄量も中位だ。
大量の発電を 行うためには 中間に 発電機と言う 運動Eの損失は介在するものの 現在では 電磁誘導現象を利用する方法しかない。 電磁誘導現象とは 発電機を使い 発電することで 備蓄機能はない。
発電機を使う発電は 従来型と言われ 風力発電(運動E→発電機)火力発電(熱E→発電機)水力発電(位置E→発電機)があり 新型としては 地熱発電(熱E→発電機)原子力発電(核E→熱E→発電機)がある。 最近研究されている 波力発電は 風力発電と 同じ発電方法でしょう。
CO2排出基準では 使用電力 1KWh当たり 555gと 計算されている。 従来型の発電は 使用電力と生産電力とは ほぼ 同じだから CO2を出さない発電は 太陽光発電 地熱発電 風力発電 水力発電 原子力発電 等 に 限られて来る。
そのように考えていたら 交通整理者から 「どうぞ お通り下さい」 と 声をかけられ 現実に戻った。
Posted by 無陀仏 at 16:00│Comments(0)
│日記 エッセイ