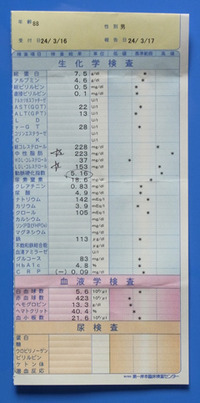2009年09月20日
篠路天然藍染め
 丸井今井百貨店の 地下入り口付近の コンコースに 旧篠路町地区で 栽培されている 藍を使った 藍染め製品が 展示されていた。 篠路は 開拓時代(明治16年)から 徳島県人の 滝本五郎氏によって 藍の生産に 力を入れていた地域だ。 藍染め製品の 元となる 「すくも」や 藍玉は 徳島県が 今でも 日本一の 生産量を誇っている。
丸井今井百貨店の 地下入り口付近の コンコースに 旧篠路町地区で 栽培されている 藍を使った 藍染め製品が 展示されていた。 篠路は 開拓時代(明治16年)から 徳島県人の 滝本五郎氏によって 藍の生産に 力を入れていた地域だ。 藍染め製品の 元となる 「すくも」や 藍玉は 徳島県が 今でも 日本一の 生産量を誇っている。 北海道では 開拓の初めに 有珠(うす)郡伊達・静内郡・余市郡・札幌郡篠路に 移住した 徳島県の人たちが 藍の栽培を試み すくもを 生産していた。 その中でも 伊達が 一番早く 明治7年(1874年)から 栽培を始めている。 伊達市では 北黄金町で 今も 藍の生産が続いている。
藍の生産は 明治30年(1897年)頃から インド藍が 明治36年(1903年)頃に ドイツから インデイゴ・ブルー染料が それぞれ 輸入され 一気に 衰退した。
藍には 殺菌作用があり 靴下・足袋を染め 水虫予防に 或いは包帯に用い 殺菌をしている。 藍は 衣服や 和紙の 防虫に また 肌荒れを防ぎ 冷え性にも効くとか。 さらに 鎮静効果もあるので 枕や布団にも 使われる。 戦国の武将は 下着を 殺菌・殺虫力のある 藍染めにして 戦いに臨んだとか。
昔 ジーンズの 青い色は ガラガラ蛇を 防ぐためとか言われていたが インデゴ・ブルーの 化学成分には そんな効果は 見当たらない。 ゴールドラッシュの アメリカの砂漠で 青い色が 清涼に見え 防蛇神話ができたのでしょう。 ただし 本藍で染めたものは 前項で 述べたとおりの効果はある。
藍は 葉を収穫し 発酵・熟成させ「すくも」にする。 販売の便利のため 脆い性質の「すくも」を 臼で搗いて 粘りのある 藍玉に 仕上げることもある。 「すくも」も藍玉も 酸性のため 水に不溶性である。 そこで 水溶性の溶液にする工程の「藍建て」を行う。 例えば 「天然灰汁発酵建て(てんねんあくはっこうだて)」と言う方法は 「すくも」に 灰汁・酒・ふすま等を混ぜ アルカリ性にして バクテリアの力で 発酵させる。 このアルカリ化工程を経て 再び 水溶性の 藍液に 還元され 天然藍の染色が 可能になる。
北海道の開発と 徳島県との 関係は濃い。 空知の雨竜地域には 徳島藩主蜂須賀氏の名が残る「蜂須賀農場」がある。 藍の青色は ジャパン・ブルー と 言われるほど 独特だ。 中国の荀子も「青は藍より出でて 藍より青し」と 言う。 これに倣い 日本では 弟子が 師匠を超え 優れていることを 「出藍(しゅつらん)の誉れ」と言う。
注 「すくも」と言う 「漢字」 は 「草」冠に 「染」 と書く。
Posted by 無陀仏 at 16:00│Comments(2)
│日記 エッセイ
この記事へのコメント
伊達は有名ですが、篠路でも藍染め続いているのですね。
私の住んでいる地区も徳島から入植(実家も含め)。
実家では、戦前、藍やハッカを作ったそうです。
私は、故人になられた郷土史研究家の方から教えてもらっていましたが、残念なことに地元では、藍を作っていたことも忘れられている状態です。
今年、徳島から種を取り寄せ、藍つくりにチャレンジ。
種まきが遅れたのもあるのですが発芽率が悪く、現在の藍の状態は、ハンカチ1枚染めるのがやっとな状態。
懲りずに来年もチャレンジの予定です。
私の住んでいる地区も徳島から入植(実家も含め)。
実家では、戦前、藍やハッカを作ったそうです。
私は、故人になられた郷土史研究家の方から教えてもらっていましたが、残念なことに地元では、藍を作っていたことも忘れられている状態です。
今年、徳島から種を取り寄せ、藍つくりにチャレンジ。
種まきが遅れたのもあるのですが発芽率が悪く、現在の藍の状態は、ハンカチ1枚染めるのがやっとな状態。
懲りずに来年もチャレンジの予定です。
Posted by さむ at 2009年09月20日 21:11
さむ 様
おきな草 から
私の 家内の ご先祖様も 徳島県人です。 私の 父方は 徳島県の隣の 香川県です。
後志管内では 余市地区で 藍が栽培されていたことは 事実です。 藍栽培の伝統が残る 地域に 生まれ育ち 幸せですね。
入植した先人は 何回も 藍の栽培に 失敗しています。
めげずに 藍(愛)情を持って 頑張れ と 応援を致します。
おきな草 から
私の 家内の ご先祖様も 徳島県人です。 私の 父方は 徳島県の隣の 香川県です。
後志管内では 余市地区で 藍が栽培されていたことは 事実です。 藍栽培の伝統が残る 地域に 生まれ育ち 幸せですね。
入植した先人は 何回も 藍の栽培に 失敗しています。
めげずに 藍(愛)情を持って 頑張れ と 応援を致します。
Posted by おきな草 at 2009年09月21日 09:37